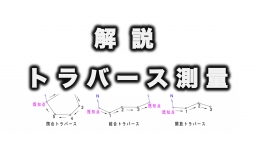DX(デジタルトランスフォーメーション)は、もはや説明不要のワードになった。
しかしDXにはいろいろな解釈が「DXを推進するには、AIやIoTを導入すればいい」と安易に捉えられている節もある。
そこでDXの定義を改めて整理し、革新のテコとなるAI活用の意義について考えてみたい。
DX(デジタルトランスフォーメーション)は、もともとスウェーデン・ウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が2004年に提唱した概念だ。この概念はデジタル技術が人々の生活のあらゆる側面において大きなインパクトを与えることを示唆していた。
2010年代になると、DXはビジネスの文脈で語られるようになる。これはIT企業が他の産業へ進出し、経済活動の根本となるコスト構造を大きく変えたことと無関係ではないだろう。

アメリカの大手レンタルビデオ・DVDチェーンのブロックバスター社は、Netflixなどインターネット動画配信サービスに圧迫され、2010年に倒産手続を申請した。
サンフランシスコ最大のタクシー会社イエローキャブは、UberやLyftが展開するライドシェアとの競争に敗れて2016年に破産申請を行った。大手玩具量販店のトイザらスは、Amazon等のインターネット通販サービスの爆発的な成長により、2018年に米国事業の清算を開始している。従来のコスト構造を前提としたビジネスモデルの存続が困難になっているのだ。
このようなディスラプター(破壊者)に対抗するために、伝統的な企業は新たなコスト構造に適した形へとビジネスモデルを、組織を、そしてマインドセットを変えていかなければならない。そこには業務を効率化するための補助ツールとしてICTを活用するという従来のデジタル化とは違った意味合いがある。
総務省の「令和元年度版 情報通信白書」では、デジタルトランスフォーメーションを「ICTと産業が一体化することでビジネスモデル自体を変革する」と定義し、従来の情報化/ICT活用との違いを定義している。
日本に目を向けてみると、企業がDXという言葉を日常使いするようになったきっかけは、2018年に経済産業省が発表した「DXレポート」だろう。
老朽化、複雑化、ブラックボックス化している既存の基幹システム(レガシーシステム)は、データを活用する上での妨げとなり、2025年までにレガシーシステムを刷新しないと以降5年間で最大12兆円の経済損失が生じると推定した。これは「2025年の崖」とも呼ばれ、政府機関が発表する資料としては異例の危機感に満ちた内容になっていたのだ。
ここで「レガシーシステムの刷新は、AmazonやUberが巻き起こした産業構造を変える現象と同じなのだろうか」と疑問に思う人もいるだろう。
実際、デジタルトランスフォーメーションの定義は曖昧であり、人によって解釈が違う。従来から行われているICTを活用した業務効率化についても「守りのDX」と定義されることもある。
そのような状況の中、経済産業省はさらに2020年に「DXレポート2」を発表。前回のDXレポートで、「DX=レガシーシステム刷新」という本質ではない解釈が是になってしまったということで、改めてDXを定義している。
初回に発表されたDXレポートが、なぜレガシーシステムの刷新を強く打ち出したかというと「企業はデータを活用する必要があるが、データが活用できる状態にない」というメッセージがあったと受け取っている。

破壊者たるGAFA(ガーファ)やFANG(ファング)の躍進の一番の理由は、データにある。これらの企業の破壊的イノベーションにより「データは21世紀の石油」とまで言われるようになった。
Amazonは、20年前も今も「協調フィルタリング」を活用したレコメンドエンジンに支えられている。
協調フィルタリングは「自分は持っていないが、自分に似た人が持っている商品は自分が欲しい商品である」という仮説に基づいている。関連した商品だけでなく、購買データをもとに人と人との類似性を定義し、自分が似た人が持っていて、自分が持っていない商品を表示する。
これによって自分が思ってもみなかった商品、それも気に入る商品が見つかり、顧客の満足感が向上するとともに、買い上げ点数が向上する。
Netflixは、利用者の視聴・評価データをもとに、その人の好みに合うコンテンツを予測しておすすめする「Cinematch(シネ・マッチ)」と呼ばれるレコメンドエンジンを開発した。精緻なマッチング性能で知られ、現在のNetflixにも引き継がれている。
Netflixはこのレコメンドエンジンにかなり力を入れ、後に賞金100万ドルを懸けたアルゴリズムコンペティションを開催するようになった。
両社ともデータを活用することで自社のキャッシュフローを改善し、顧客にパーソナライズされた新しい体験を与えている。そして既存産業を脅かす存在にまで成長したのだ。
破壊者は創業当時からデジタル企業なので、データ活用が比較的簡単にできる。しかし伝統的なプレイヤーは、そうではない。紙の情報も残っているし、熟練者の感性と経験に頼っている部分もある。基幹システムも部署ごとに部分最適化されて、結果、蓄積されたデータがあちこちに点在している。
そこで「DXレポート」でも強調されていた基幹システムの刷新が必要となるのだが、基幹システムは複雑化・サイロ化されていて、簡単に刷新できるものではない。
しかし、それを乗り越えなければいけない時期に来ているのだ。
こうしたデータの問題をクリアし、データを“正しく”蓄積できたその先に、DXで求められる「データドリブン経営(データに基づき、客観性の高い意思決定を行う)」がある。
データを蓄積できたとしてもそのままでは必ずしも価値がない。データから気づきを得てあるいはデータを基盤として、事業構造を変革し、新たな顧客体験を生む必要があるからだ。

データ活用には段階がある。最初の段階が収集したデータを必要な人が見られる環境にする「データの閲覧」だ。
さらにそのデータを様々な切り口から集計する「データの集計」が次の段階。そしてデータの集合体から傾向を探る「統計的な分析」、そして「機械学習等のAIを活用した予測」へと発展する。収集したデータの活用を高度化させて価値を上げていくということが競争力の源泉となるのだ。
「令和2年版 情報通信白書」によると、企業活動において活用しているデータの種類について分析を行ったところ、POSやeコマースによる販売記録、IoTデータを含む自動取得データの活用が5年前と比較して大きく進展したことが分かった。
この5年でデータ分析による企業経営の高度化が進められていることがうかがえる。
一方でデータの分析手法については、「データの閲覧」と「集計」が企業規模や産業を問わず約7割と多くなっているが、「機械学習・ディープラーニングなど人工知能(AI)を活用した予測」は総じて低い。
AIを活用している企業は大企業が18%、中小企業で3.9%と開きがあることから、資金面・人材面で差が表れていると白書では分析しているが、大企業でも2割以下と少ないことに変わりはない。AIを活用してより深い気づきを得ることが、競争力を高めると言えるだろう。
ここでAIを活用してDXに取り組む事例を紹介しよう。
1919年、トラック4台で出発したヤマトグループは、「宅急便」を開発する等のイノベーションを生み出してきた。
2018年に発表した経営構造改革プラン「YAMATO NEXT100」では、「宅急便のDX」を事業構造改革の柱のひとつとして掲げた。現在の宅急便では、全国から集まる荷物を70か所の「ベース」でエリア内のセンター向けに一次仕分け後、全国3700カ所あるセンターでコース別に二次仕分けをしている。
これを2021年以降は、デジタル化・ロボティクス・ファクトリーオートメーションにより、ベースで各センターのコース別に仕分けし、センターでは仕分け不要に変更する。徹底したデータ分析とAI活用で輸配送工程とオペレーション全体を最適化・標準化・低コスト化につなげる。
2021年4月からは、デジタル化の司令塔になる「デジタル機能本部」を発足し、部門ごとにあったIT関連組織を1つにまとめた。
DX人材育成に向けた新しい教育プログラムを「Yamato Digital Academy」を本格的に展開し、3年で1000名規模のグループ社員の受講を予定している。
ミスミ社は、機械メーカー向けに部品のカタログ販売をする老舗メーカーだ。ミスミブランドの他に他社ブランドの商品も広く取り扱う流通事業も展開している。
扱う商品数は3300万点以上、長さや太さのバリエーションを含めると800垓(垓=1兆の1億倍)にも及ぶ。生産材プラットフォームへの業態改革を掲げ、グローバルで確実短納期を実現し、顧客に時間単価を提供する「時間戦略」を打ち出している。
そのうちの一手が「meviy」だ。製造業においては、3D-CADによるデジタル化が進むものの、部品調達に関しては、手配図面の作成や見積依頼、納期確認、交渉といった工程を人手に頼っている。
meviyでは3D-CADの部品データをアップロードするだけでAIが自動で金額と納期を計算し、最短1日で出荷する。部品点数1500点で構成される設備の部品調達の場合、従来は約1000時間かかっていたところを、約80時間の作業で済む計算だ。
3D-CADのデータはソフトウェアによって形式が違い、データから仕様を読み取るのは非常に難易度が高い。国内のITベンダーには開発を断られ、世界中を訪ねて技術を探したという。
商品領域、素材バリエーションを広げていき、現在の利用ユーザーは4万人以上。リピート率は8割を超える。日本産業技術大賞(文部科学大臣賞)を受賞する等、その革新性は各方面から高く評価されている。
トライアル社では、九州地方を中心に250店舗以上のスーパーセンター(食料品や衣料品、住居関連商品を一つのフロアに集めた業態)を展開している。
セルフレジ機能を搭載した買い物カート「スマートショッピングカート」や、人や棚の動きを検知する「リテールAIカメラ」などを店舗内に設置。新たな買い物体験を来店者に提供するとともに、収集したデータを約260社のメーカーや卸売業者と共有している。
特筆するべきは、店舗内のシステムをすべてグループ企業のRetail AI社が自ら開発していることだ。Retail AI社には、国内に約50人、中国に約300人のエンジニアが在籍する。
そしてこのシステムをプラットフォームとして広めるべく、競合となる他の小売企業にも展開している。2019年には小売・卸・流通・メーカー・冷蔵ショーケースメーカーの各プレイヤーが連携するリテール AI プラットフォームプロジェクト「リアイル」を発足させ、流通業界の構造改革に取り組んでいる。
これまでの内容を振り返って整理しよう。
新型コロナウイルスにより、新しい生活様式が日常のものとなった。企業の多くが不測の事態は今後も当たり前のように発生し、これからも革新を持続させて対応しなければならないということを痛感したはずだ。
持続的な革新を実現するために、AIを活用する未来はもうそこまで来ている。
しかしDXにはいろいろな解釈が「DXを推進するには、AIやIoTを導入すればいい」と安易に捉えられている節もある。
そこでDXの定義を改めて整理し、革新のテコとなるAI活用の意義について考えてみたい。
DXの本当の意味とは?
DX(デジタルトランスフォーメーション)は、もともとスウェーデン・ウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が2004年に提唱した概念だ。この概念はデジタル技術が人々の生活のあらゆる側面において大きなインパクトを与えることを示唆していた。
2010年代になると、DXはビジネスの文脈で語られるようになる。これはIT企業が他の産業へ進出し、経済活動の根本となるコスト構造を大きく変えたことと無関係ではないだろう。

アメリカの大手レンタルビデオ・DVDチェーンのブロックバスター社は、Netflixなどインターネット動画配信サービスに圧迫され、2010年に倒産手続を申請した。
サンフランシスコ最大のタクシー会社イエローキャブは、UberやLyftが展開するライドシェアとの競争に敗れて2016年に破産申請を行った。大手玩具量販店のトイザらスは、Amazon等のインターネット通販サービスの爆発的な成長により、2018年に米国事業の清算を開始している。従来のコスト構造を前提としたビジネスモデルの存続が困難になっているのだ。
このようなディスラプター(破壊者)に対抗するために、伝統的な企業は新たなコスト構造に適した形へとビジネスモデルを、組織を、そしてマインドセットを変えていかなければならない。そこには業務を効率化するための補助ツールとしてICTを活用するという従来のデジタル化とは違った意味合いがある。
総務省の「令和元年度版 情報通信白書」では、デジタルトランスフォーメーションを「ICTと産業が一体化することでビジネスモデル自体を変革する」と定義し、従来の情報化/ICT活用との違いを定義している。
日本に目を向けてみると、企業がDXという言葉を日常使いするようになったきっかけは、2018年に経済産業省が発表した「DXレポート」だろう。
老朽化、複雑化、ブラックボックス化している既存の基幹システム(レガシーシステム)は、データを活用する上での妨げとなり、2025年までにレガシーシステムを刷新しないと以降5年間で最大12兆円の経済損失が生じると推定した。これは「2025年の崖」とも呼ばれ、政府機関が発表する資料としては異例の危機感に満ちた内容になっていたのだ。
ここで「レガシーシステムの刷新は、AmazonやUberが巻き起こした産業構造を変える現象と同じなのだろうか」と疑問に思う人もいるだろう。
実際、デジタルトランスフォーメーションの定義は曖昧であり、人によって解釈が違う。従来から行われているICTを活用した業務効率化についても「守りのDX」と定義されることもある。
そのような状況の中、経済産業省はさらに2020年に「DXレポート2」を発表。前回のDXレポートで、「DX=レガシーシステム刷新」という本質ではない解釈が是になってしまったということで、改めてDXを定義している。
DXにおいてデジタルデータが果たす役割
初回に発表されたDXレポートが、なぜレガシーシステムの刷新を強く打ち出したかというと「企業はデータを活用する必要があるが、データが活用できる状態にない」というメッセージがあったと受け取っている。

破壊者たるGAFA(ガーファ)やFANG(ファング)の躍進の一番の理由は、データにある。これらの企業の破壊的イノベーションにより「データは21世紀の石油」とまで言われるようになった。
Amazonは、20年前も今も「協調フィルタリング」を活用したレコメンドエンジンに支えられている。
協調フィルタリングは「自分は持っていないが、自分に似た人が持っている商品は自分が欲しい商品である」という仮説に基づいている。関連した商品だけでなく、購買データをもとに人と人との類似性を定義し、自分が似た人が持っていて、自分が持っていない商品を表示する。
これによって自分が思ってもみなかった商品、それも気に入る商品が見つかり、顧客の満足感が向上するとともに、買い上げ点数が向上する。
Netflixは、利用者の視聴・評価データをもとに、その人の好みに合うコンテンツを予測しておすすめする「Cinematch(シネ・マッチ)」と呼ばれるレコメンドエンジンを開発した。精緻なマッチング性能で知られ、現在のNetflixにも引き継がれている。
Netflixはこのレコメンドエンジンにかなり力を入れ、後に賞金100万ドルを懸けたアルゴリズムコンペティションを開催するようになった。
両社ともデータを活用することで自社のキャッシュフローを改善し、顧客にパーソナライズされた新しい体験を与えている。そして既存産業を脅かす存在にまで成長したのだ。
破壊者は創業当時からデジタル企業なので、データ活用が比較的簡単にできる。しかし伝統的なプレイヤーは、そうではない。紙の情報も残っているし、熟練者の感性と経験に頼っている部分もある。基幹システムも部署ごとに部分最適化されて、結果、蓄積されたデータがあちこちに点在している。
そこで「DXレポート」でも強調されていた基幹システムの刷新が必要となるのだが、基幹システムは複雑化・サイロ化されていて、簡単に刷新できるものではない。
しかし、それを乗り越えなければいけない時期に来ているのだ。
DX推進にAIはなぜ必要か
こうしたデータの問題をクリアし、データを“正しく”蓄積できたその先に、DXで求められる「データドリブン経営(データに基づき、客観性の高い意思決定を行う)」がある。
データを蓄積できたとしてもそのままでは必ずしも価値がない。データから気づきを得てあるいはデータを基盤として、事業構造を変革し、新たな顧客体験を生む必要があるからだ。

データ活用には段階がある。最初の段階が収集したデータを必要な人が見られる環境にする「データの閲覧」だ。
さらにそのデータを様々な切り口から集計する「データの集計」が次の段階。そしてデータの集合体から傾向を探る「統計的な分析」、そして「機械学習等のAIを活用した予測」へと発展する。収集したデータの活用を高度化させて価値を上げていくということが競争力の源泉となるのだ。
「令和2年版 情報通信白書」によると、企業活動において活用しているデータの種類について分析を行ったところ、POSやeコマースによる販売記録、IoTデータを含む自動取得データの活用が5年前と比較して大きく進展したことが分かった。
この5年でデータ分析による企業経営の高度化が進められていることがうかがえる。
一方でデータの分析手法については、「データの閲覧」と「集計」が企業規模や産業を問わず約7割と多くなっているが、「機械学習・ディープラーニングなど人工知能(AI)を活用した予測」は総じて低い。
AIを活用している企業は大企業が18%、中小企業で3.9%と開きがあることから、資金面・人材面で差が表れていると白書では分析しているが、大企業でも2割以下と少ないことに変わりはない。AIを活用してより深い気づきを得ることが、競争力を高めると言えるだろう。
AIが支えるDXの事例
ここでAIを活用してDXに取り組む事例を紹介しよう。
物流の構造を再構築「ヤマトグループ」
1919年、トラック4台で出発したヤマトグループは、「宅急便」を開発する等のイノベーションを生み出してきた。
2018年に発表した経営構造改革プラン「YAMATO NEXT100」では、「宅急便のDX」を事業構造改革の柱のひとつとして掲げた。現在の宅急便では、全国から集まる荷物を70か所の「ベース」でエリア内のセンター向けに一次仕分け後、全国3700カ所あるセンターでコース別に二次仕分けをしている。
これを2021年以降は、デジタル化・ロボティクス・ファクトリーオートメーションにより、ベースで各センターのコース別に仕分けし、センターでは仕分け不要に変更する。徹底したデータ分析とAI活用で輸配送工程とオペレーション全体を最適化・標準化・低コスト化につなげる。
2021年4月からは、デジタル化の司令塔になる「デジタル機能本部」を発足し、部門ごとにあったIT関連組織を1つにまとめた。
DX人材育成に向けた新しい教育プログラムを「Yamato Digital Academy」を本格的に展開し、3年で1000名規模のグループ社員の受講を予定している。
顧客へ時間単価を提供するプラットフォームを構築「ミスミ」
ミスミ社は、機械メーカー向けに部品のカタログ販売をする老舗メーカーだ。ミスミブランドの他に他社ブランドの商品も広く取り扱う流通事業も展開している。
扱う商品数は3300万点以上、長さや太さのバリエーションを含めると800垓(垓=1兆の1億倍)にも及ぶ。生産材プラットフォームへの業態改革を掲げ、グローバルで確実短納期を実現し、顧客に時間単価を提供する「時間戦略」を打ち出している。
そのうちの一手が「meviy」だ。製造業においては、3D-CADによるデジタル化が進むものの、部品調達に関しては、手配図面の作成や見積依頼、納期確認、交渉といった工程を人手に頼っている。
meviyでは3D-CADの部品データをアップロードするだけでAIが自動で金額と納期を計算し、最短1日で出荷する。部品点数1500点で構成される設備の部品調達の場合、従来は約1000時間かかっていたところを、約80時間の作業で済む計算だ。
3D-CADのデータはソフトウェアによって形式が違い、データから仕様を読み取るのは非常に難易度が高い。国内のITベンダーには開発を断られ、世界中を訪ねて技術を探したという。
商品領域、素材バリエーションを広げていき、現在の利用ユーザーは4万人以上。リピート率は8割を超える。日本産業技術大賞(文部科学大臣賞)を受賞する等、その革新性は各方面から高く評価されている。
AIで新たな買い物体験を生み出す「トライアルグループ」
トライアル社では、九州地方を中心に250店舗以上のスーパーセンター(食料品や衣料品、住居関連商品を一つのフロアに集めた業態)を展開している。
セルフレジ機能を搭載した買い物カート「スマートショッピングカート」や、人や棚の動きを検知する「リテールAIカメラ」などを店舗内に設置。新たな買い物体験を来店者に提供するとともに、収集したデータを約260社のメーカーや卸売業者と共有している。
特筆するべきは、店舗内のシステムをすべてグループ企業のRetail AI社が自ら開発していることだ。Retail AI社には、国内に約50人、中国に約300人のエンジニアが在籍する。
そしてこのシステムをプラットフォームとして広めるべく、競合となる他の小売企業にも展開している。2019年には小売・卸・流通・メーカー・冷蔵ショーケースメーカーの各プレイヤーが連携するリテール AI プラットフォームプロジェクト「リアイル」を発足させ、流通業界の構造改革に取り組んでいる。
持続的な革新を実現するためにはAIが必要不可欠
これまでの内容を振り返って整理しよう。
- 政府は「DXレポート2」でDXを3段階で定義し、企業に具体的なアクションを促した。
- 破壊的イノベーションの源泉がデータであったように、伝統的なプレイヤーもデータ活用でDXを推進する必要がある。
- データ活用を高度化するにはAIの活用が不可欠だ
新型コロナウイルスにより、新しい生活様式が日常のものとなった。企業の多くが不測の事態は今後も当たり前のように発生し、これからも革新を持続させて対応しなければならないということを痛感したはずだ。
持続的な革新を実現するために、AIを活用する未来はもうそこまで来ている。
参考:
総務省|令和元年版 情報通信白書|デジタル・トランスフォーメーション-あらゆる産業にICTが一体化していくhttps://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r01/html/nd121500.htmlDX レポート 2 中間取りまとめ (概要) - 経済産業省【PDF】https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation_kasoku/pdf/20201228_2.pdf総務省|令和2年版 情報通信白書|日本企業におけるデータ活用の現状https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r02/html/nd132110.html
デジタル人材の育成へ向け、「Yamato Digital Academy」をスタート | ヤマトホールディングス株式会社https://www.yamato-hd.co.jp/news/2020/20210317_04.html?_ga=2.250103236.330215721.1619248767-344113063.1619248766
アニュアルレポート | IR資料室 | 株主・投資家情報 | 株式会社ミスミグループ本社https://www.misumi.co.jp/ir/library/annual_report.html
画像:Shutterstock
総務省|令和元年版 情報通信白書|デジタル・トランスフォーメーション-あらゆる産業にICTが一体化していくhttps://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r01/html/nd121500.htmlDX レポート 2 中間取りまとめ (概要) - 経済産業省【PDF】https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation_kasoku/pdf/20201228_2.pdf総務省|令和2年版 情報通信白書|日本企業におけるデータ活用の現状https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r02/html/nd132110.html
デジタル人材の育成へ向け、「Yamato Digital Academy」をスタート | ヤマトホールディングス株式会社https://www.yamato-hd.co.jp/news/2020/20210317_04.html?_ga=2.250103236.330215721.1619248767-344113063.1619248766
アニュアルレポート | IR資料室 | 株主・投資家情報 | 株式会社ミスミグループ本社https://www.misumi.co.jp/ir/library/annual_report.html
画像:Shutterstock
WRITTEN by

建設土木のICT活用など、
デジコンからの最新情報をメールでお届けします