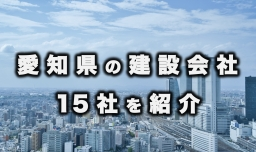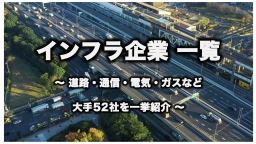コンクリートは現代建設における最も重要な建設材料の一つであり、その品質は構造物の安全性や耐久性に直結する。しかし、優れた配合設計がなされていても、施工方法が適切でなければ期待される性能を発揮することはできない。
コンクリート施工の基本は「練り混ぜてから打ち終わるまでの時間管理」「材料分離を起こさない運搬・打込み方法」「確実な締固め」「適切な養生」の4つである。
これらのプロセスを適切に行うことで、設計通りの強度と耐久性を持つコンクリート構造物を実現することができる。
本記事では、コンクリートの運搬から打込み、締固め、仕上げ、養生までの一連の施工プロセスについて、現場で役立つ基本知識と実践的なポイントを解説する。
コンクリートは、練り混ぜ後速やかに運搬し、直ちに打ち込み、十分に締め固めなければならない。運搬に関する重要なポイントは以下のとおりである。
コンクリートの運搬における時間管理は非常に重要で、特に暑中コンクリートでは硬化が早まるため、時間制限に特に注意が必要である。
スランプの小さい硬練りコンクリートはダンプトラックを用いることもできるが、一般にはアジテータトラックで運搬中にゆっくりとドラムを回転させて分離を防ぐ。
アジテータトラックはミキサー機能を持つ運搬車で、コンクリートの品質維持に有効である。
一方、ダンプトラックで運搬する場合は、振動や長時間の運搬によって材料分離が起こりやすいため、注意が必要である。
コンクリートをバケットに受け、これを直ちに打込み箇所までクレーンで運搬する方法は、材料分離を最も少なくする方法の一つである。バケットでの運搬は、コンクリートの品質低下が少ないという利点がある。
高いところからシュートを用いてコンクリートを打設する場合には、シュートの使用を原則とする。
やむを得ず自由落下によるシュートを用いる場合には、シュートの傾きは材料分離を起こさない程度のものであるため、水平2に対して鉛直1程度を標準とする。
縦シュートは材料分離が発生しにくい特性を持つが、適切な角度で設置しないと、分離が生じる可能性がある。
コンクリートの打込みにあたっては、以下のポイントに注意する。
打込み時のコールドジョイント(上層と下層の不連続面)が発生しないように打継ぎ時間間隔などを適切に設定する必要がある。
許容打重ね時間間隔の標準は、外気温25℃を超えるときで2.0時間、25℃以下のときで2.5時間である。
コンクリートの締固めは、内部の空隙を少なくし、鉄筋、埋設物などと密着させ、コンクリートが均一で密実になるように十分行う必要がある。
内部振動機の挿入位置が適切でないと、コンクリートの締固めが不十分となり、強度不足や耐久性の低下を招く恐れがある。
打継目は、できるだけせん断力の小さな位置に設け、打継目に作用する部材の圧縮力の作用方向と直交させるのを原則とする。
やむを得ず、せん断力の大きい位置に打継目を設ける場合には、打継目にはキーまたは溝を設けるか、鉄筋を主として打継目の部分を補強する。
鉄筋による補強を受けるおそれのある海洋および港湾コンクリートや塩害の受けやすい道路橋においては、打継目はできるだけ設けないようにする。
水密を要するコンクリートにおいては、所要の水密性が得られるように、適切な間隔で打継目を設けなければならない。
水平打継目の型枠に接する縁は、できるだけ水平な直線になるようにする。
コンクリートを打継ぐ場合には、既に打ち込まれたコンクリートの表面のレイタンス、品質の悪いコンクリート、緩んだ骨材粒を完全に取り除き、表面を粗にした後(グリーンカット)、十分吸水させる。
新たなコンクリートを打ち継ぐ直前にモルタルを敷く方法は、新旧コンクリートの付着をよくする。
硬化前の処理としては、高圧の空気および水でコンクリート表面の薄層を除去する。硬化後の処理としては、表面をワイヤブラシを用いて粗にする。
鉛直打継目の施工にあたっては、打継面の型枠を強固に支持する。
既に打ち込まれた硬化したコンクリートの打継面は、ワイヤブラシで表面を削るか、チッピング等により、表面を粗にして十分吸水させ、セメントペースト、モルタルあるいは湿潤面用エポキシ樹脂等を塗った後、新しくコンクリートを打ち継ぐ。
コンクリートの打込みにあたっては、打継面が十分に密着するように締め固めなければならない。また、新しいコンクリートの打込みを適当な時期に再振動締固めを行う。
水密を要するコンクリートの水平打継目では、止水板を用いるのを原則とする。
締固め後、ほぼ所定の高さおよび形に沿ったコンクリート表面は、み出た水がなくなるか、水を取り除いた後に、木ゴテで荒仕上げを行う。
指で押しても、へこみにくい程度に固まったら、こて鏝を押し回しながらセメントペーストを押し固め、滑らかで密実な面に仕上げる。
コンクリートの打込み後、コンクリートが十分な強度を発現するまで、有害な作用から保護し、またセメントの硬化作用を十分に発揮させるとともに、乾燥に伴う収縮やひび割れの発生をできるだけ少なくするための作業を養生という。
コンクリートの施工は、その品質を左右する重要なプロセスである。適切な運搬方法の選択、打込み時の注意点、確実な締固め、丁寧な仕上げ、そして十分な養生を行うことで、設計通りの性能を持つコンクリート構造物を実現することができる。
特に重要なポイントとしては以下が挙げられる。
これらの基本を守ることで、耐久性に優れた高品質なコンクリート構造物を構築することができる。また、近年では様々な新技術や施工方法が開発されているため、最新の技術情報も積極的に取り入れることが大切である。
コンクリート施工の基本は「練り混ぜてから打ち終わるまでの時間管理」「材料分離を起こさない運搬・打込み方法」「確実な締固め」「適切な養生」の4つである。
これらのプロセスを適切に行うことで、設計通りの強度と耐久性を持つコンクリート構造物を実現することができる。
本記事では、コンクリートの運搬から打込み、締固め、仕上げ、養生までの一連の施工プロセスについて、現場で役立つ基本知識と実践的なポイントを解説する。
1. コンクリートの運搬・打込み・締固め
1-1. 運搬
コンクリートは、練り混ぜ後速やかに運搬し、直ちに打ち込み、十分に締め固めなければならない。運搬に関する重要なポイントは以下のとおりである。
- 練混ぜから打ち終わるまでの時間は、原則として外気温が25℃を超えるときで1.5時間以内、25℃以下のときで2時間以内を標準とする
- 運搬中に著しい材料分離を認めたときは、十分に練り直して均質なものとしてから用いる
- 固まり始めたコンクリートは練り直して用いてはならない
コンクリートの運搬における時間管理は非常に重要で、特に暑中コンクリートでは硬化が早まるため、時間制限に特に注意が必要である。
1-2. 運搬車
スランプの小さい硬練りコンクリートはダンプトラックを用いることもできるが、一般にはアジテータトラックで運搬中にゆっくりとドラムを回転させて分離を防ぐ。
アジテータトラックはミキサー機能を持つ運搬車で、コンクリートの品質維持に有効である。
一方、ダンプトラックで運搬する場合は、振動や長時間の運搬によって材料分離が起こりやすいため、注意が必要である。
1-3. バケット(コンクリートホッパー)
コンクリートをバケットに受け、これを直ちに打込み箇所までクレーンで運搬する方法は、材料分離を最も少なくする方法の一つである。バケットでの運搬は、コンクリートの品質低下が少ないという利点がある。
1-4. シュート
高いところからシュートを用いてコンクリートを打設する場合には、シュートの使用を原則とする。
やむを得ず自由落下によるシュートを用いる場合には、シュートの傾きは材料分離を起こさない程度のものであるため、水平2に対して鉛直1程度を標準とする。
縦シュートは材料分離が発生しにくい特性を持つが、適切な角度で設置しないと、分離が生じる可能性がある。
1-5. 打込み
コンクリートの打込みにあたっては、以下のポイントに注意する。
- 打設前には、吸水するおそれがあるところは湿らせておく
- コンクリートは、練混ぜから打ち終わるまでの時間は、原則として外気温が25℃を超えるときで1.5時間以内、25℃以下のときで2時間以内を標準とする
- 打ち込んだコンクリートは、型枠内で横移動させてはならない
- コンクリートの1回の打込み高さは40~50 cm以下とする
- コンクリートを2層以上に分けて打ち込む場合、上層のコンクリートは下層のコンクリートが固まり始める前に打ち、上層と下層が一体となるように注意する
打込み時のコールドジョイント(上層と下層の不連続面)が発生しないように打継ぎ時間間隔などを適切に設定する必要がある。
許容打重ね時間間隔の標準は、外気温25℃を超えるときで2.0時間、25℃以下のときで2.5時間である。
- シュート、ポンプ配管、バケット、ホッパー等の吐出口から打込み箇所までの高さは1.5 m以下とし、コンクリート面にできるだけ近いところまで下げて打ち込む
- コンクリートの打込みにあたっては、できるだけ材料が分離しないようにし、鉄筋と十分に密着させ、型枠の隅々まで充填させる
- コンクリートの打込み中、表面にブリーディング水がある場合は、スポンジなどでこれを取り除く
- 打上がり速度は、一般の場合、30分につき1~1.5 m程度を標準とする
- コンクリートを地面に直接打ち込む場合は、あらかじめ均しコンクリートを敷いておく
- コンクリートの打込みにあたっては、型枠やせき板が硬化したコンクリート表面からはがれやすくするため、剥離剤を塗布する
2. コンクリートの締固め
コンクリートの締固めは、内部の空隙を少なくし、鉄筋、埋設物などと密着させ、コンクリートが均一で密実になるように十分行う必要がある。
2-1. 内部振動機の使用方法
- コンクリートの締固めには、内部振動機を用いることを原則とし、薄い壁や内部振動機の使用が困難な場所には型枠振動機を使用してもよい
- コンクリートは、打込み後速やかに十分締固め、コンクリートが鉄筋の周囲および型枠の隅々まで行き渡るようにしなければならない
- せき板に接するコンクリートは、できるだけ平坦な表面が得られるように打ち込み、締め固めなければならない
- 振動締固めにあたっては、内部振動機を下層のコンクリート中に10 cm程度挿入する
- 内部振動機は鉛直に挿入し、その間隔は振動が有効と認められる範囲の直径以下の一様な間隔とする。挿入間隔は、一般に50 cm以下とする
- 1ヶ所あたりの挿入時間は5~15秒とする
- 内部振動機の引抜きは、後に穴が残らないよう徐々に行う
- 内部振動機は、コンクリートを横移動させる目的で使用してはならない
- 再振動を行う場合には、コンクリートに悪影響が生じないように、再振動によって締固めができる範囲でなるべく遅い時期に行う
内部振動機の挿入位置が適切でないと、コンクリートの締固めが不十分となり、強度不足や耐久性の低下を招く恐れがある。
3. コンクリートの打継目
3-1. 一般
打継目は、できるだけせん断力の小さな位置に設け、打継目に作用する部材の圧縮力の作用方向と直交させるのを原則とする。
やむを得ず、せん断力の大きい位置に打継目を設ける場合には、打継目にはキーまたは溝を設けるか、鉄筋を主として打継目の部分を補強する。
鉄筋による補強を受けるおそれのある海洋および港湾コンクリートや塩害の受けやすい道路橋においては、打継目はできるだけ設けないようにする。
水密を要するコンクリートにおいては、所要の水密性が得られるように、適切な間隔で打継目を設けなければならない。
3-2. 水平打継目の施工
水平打継目の型枠に接する縁は、できるだけ水平な直線になるようにする。
コンクリートを打継ぐ場合には、既に打ち込まれたコンクリートの表面のレイタンス、品質の悪いコンクリート、緩んだ骨材粒を完全に取り除き、表面を粗にした後(グリーンカット)、十分吸水させる。
新たなコンクリートを打ち継ぐ直前にモルタルを敷く方法は、新旧コンクリートの付着をよくする。
硬化前の処理としては、高圧の空気および水でコンクリート表面の薄層を除去する。硬化後の処理としては、表面をワイヤブラシを用いて粗にする。
3-3. 鉛直打継目の施工
鉛直打継目の施工にあたっては、打継面の型枠を強固に支持する。
既に打ち込まれた硬化したコンクリートの打継面は、ワイヤブラシで表面を削るか、チッピング等により、表面を粗にして十分吸水させ、セメントペースト、モルタルあるいは湿潤面用エポキシ樹脂等を塗った後、新しくコンクリートを打ち継ぐ。
コンクリートの打込みにあたっては、打継面が十分に密着するように締め固めなければならない。また、新しいコンクリートの打込みを適当な時期に再振動締固めを行う。
水密を要するコンクリートの水平打継目では、止水板を用いるのを原則とする。
4. コンクリートの仕上げ
締固め後、ほぼ所定の高さおよび形に沿ったコンクリート表面は、み出た水がなくなるか、水を取り除いた後に、木ゴテで荒仕上げを行う。
指で押しても、へこみにくい程度に固まったら、こて鏝を押し回しながらセメントペーストを押し固め、滑らかで密実な面に仕上げる。
5. コンクリートの養生
コンクリートの打込み後、コンクリートが十分な強度を発現するまで、有害な作用から保護し、またセメントの硬化作用を十分に発揮させるとともに、乾燥に伴う収縮やひび割れの発生をできるだけ少なくするための作業を養生という。
5-1. 基本的な養生方法
- コンクリートは、打込み後、日光の直射、風等から保護し、硬化を始めるまで乾燥の防止に努める
- コンクリートの露出面は養生マット、布等をかぶせて湿潤状態に保つ。湿潤養生を行う期間は、標準的には以下の通りである。
- 日平均気温15℃以上:
普通ポルトランドセメント 5日/混合セメントB種 7日/早強ポルトランドセメント3日 - 日平均気温10℃以上:
普通ポルトランドセメント 7日/混合セメントB種 9日/早強ポルトランドセメント4日 - 日平均気温5℃以上:
普通ポルトランドセメント 9日/混合セメントB種 12日/早強ポルトランドセメント5日
- 膜養生は、十分な量の膜養生剤を適切な時期に、均一に散布し、表を標準する
- 膜養生を行うときは、コンクリート表面の水光りが消えた直後に行う
- 膜養生剤を散布するおそれのある型枠(型枠)が乾燥するおそれのある場合には、散水し、湿潤状態に保つ
- コンクリートは、十分な硬化が進むまで、硬化に必要な温度条件を保つ
- コンクリートは、養生期間に予想される振動、衝撃、荷重等の有害な作用から保護する
- 養生の方法と期間は、コンクリートの種類、気象条件、構造物の重要度などを考慮して決定する必要がある。特に、低温時や高温時には、特別な養生対策が必要となる。
まとめ
コンクリートの施工は、その品質を左右する重要なプロセスである。適切な運搬方法の選択、打込み時の注意点、確実な締固め、丁寧な仕上げ、そして十分な養生を行うことで、設計通りの性能を持つコンクリート構造物を実現することができる。
特に重要なポイントとしては以下が挙げられる。
- 練混ぜから打ち終わるまでの時間管理(外気温25℃超で1.5時間以内、25℃以下で2時間以内)
- 材料分離を防止するための適切な運搬方法の選択
- 1回の打込み高さは40~50cm以下とし、層状に打設
- 内部振動機による確実な締固め(挿入間隔50cm以下、挿入時間5~15秒)
- 打継目の適切な処理(レイタンス除去、吸水、新旧コンクリートの接着)
- 気象条件に応じた養生期間の確保
これらの基本を守ることで、耐久性に優れた高品質なコンクリート構造物を構築することができる。また、近年では様々な新技術や施工方法が開発されているため、最新の技術情報も積極的に取り入れることが大切である。
WRITTEN by

建設土木のICT活用など、
デジコンからの最新情報をメールでお届けします