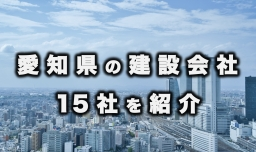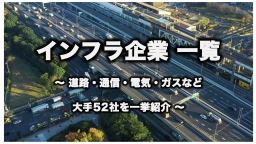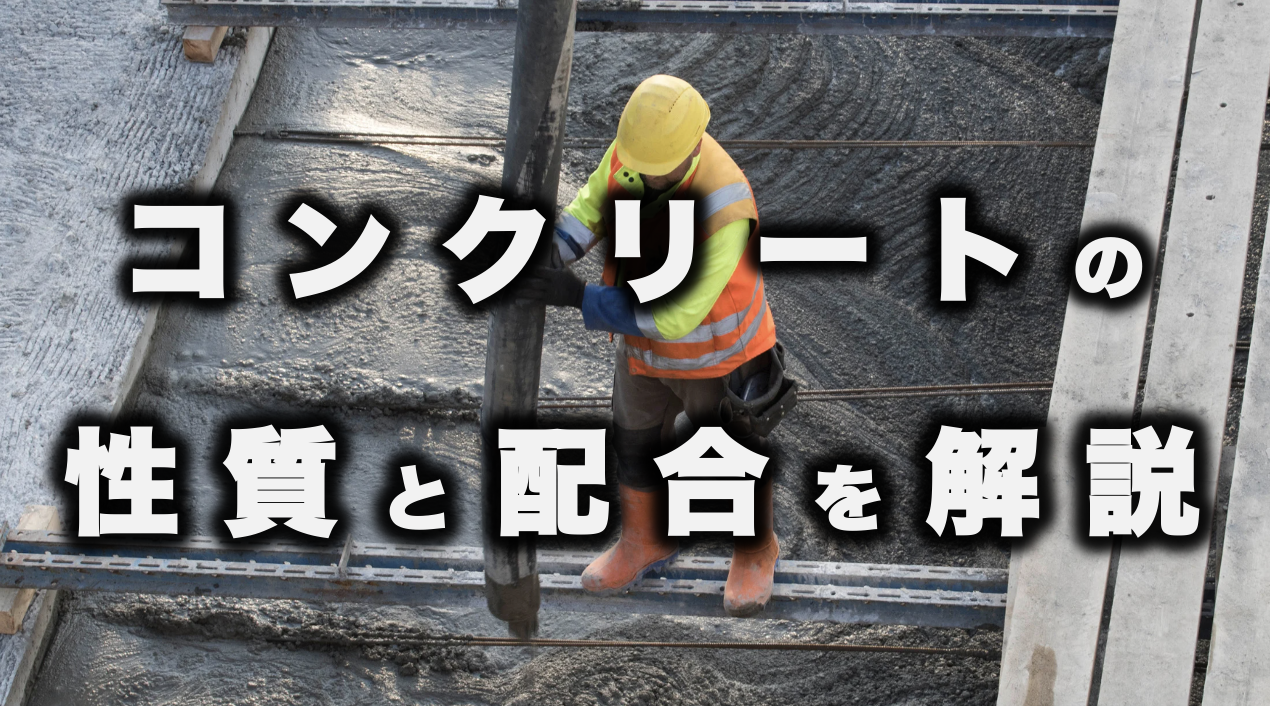
現代の建設業界において、コンクリートは最も重要な建設材料の一つである。橋梁、ビル、ダム、トンネルなど、私たちの生活インフラの多くはコンクリートによって支えられている。
しかし、一言でコンクリートと言っても、その性質や配合は用途に応じて多様に変化する。
本記事では、フレッシュコンクリートの性質から配合の基本原則、さらには特殊な環境や目的に応じた特殊コンクリートの種類まで、幅広く解説していく。
コンクリート工事に関わるエンジニアや技術者はもちろん、建設業界を志す学生にも役立つ情報を提供していく。
まだ固まっていないコンクリートを「フレッシュコンクリート」と呼ぶ。フレッシュコンクリートは、締固め、仕上げが容易で、これらの作業中において材料分離が少ないものでなければならない。これらの性質を表すために、以下の用語が用いられる。
ワーカビリティーとは、材料分離を生じることなく、運搬、打込み、締固め、仕上げなどの作業が容易にできる程度を表す性質である。
簡単に言えば、コンクリートの「扱いやすさ」のことだ。
ワーカビリティーの良いコンクリートは、型枠への充填や締固めが容易で、仕上げも綺麗にできる。一方、ワーカビリティーが悪いと、作業効率が落ちるだけでなく、密実なコンクリートを得ることが難しくなる。
コンシステンシーは、フレッシュコンクリートの変形または流動に対する抵抗の程度を表す性質である。コンシステンシーはスランプ試験で求めた値で示される。
スランプ値が大きいほど流動性が高く、小さいほど硬練りであることを意味する。適切なコンシステンシーは、工事の種類や打設条件によって異なる。
スランプは、フレッシュコンクリートの軟らかさの程度を示す指標である。スランプ試験は、一定形状の型枠にコンクリートを詰め、型枠を取り外した際のコンクリートの沈下量を測定するものだ。
コンクリートの運搬、打込み、締固めの作業に適するよう、スランプはできるだけ小さく定める。一般的な鉄筋コンクリート構造物の場合、スランプは8~12cmが標準とされることが多い。
コンクリート材料の分離を少なくするためには、適切なワーカビリティーのコンクリートを用いることがもっとも大切であり、分離を減らすために減水剤またはAE剤の活用は極めて有効である。材料分離の代表的なものには以下がある。
ブリーディングとは、コンクリートの打込み終了後に、セメントおよび骨材粒子の沈下に伴い水が表面に浮かび上がる現象を言う。
過度のブリーディングは、表面強度の低下、ひび割れの発生、水密性の低下などの原因となる。適切な配合設計と材料選定により、ブリーディングを抑制することが重要である。
レイタンスとは、ブリーディングに伴い、コンクリートモルタルまたはペーストの表面に、セメント、骨材中の微粒子、セメント水和物等からなる不純物が堆積したものを言う。
レイタンスは弱点にもなるので必ず取り除かなければならない。特に打継ぎ部分では、新しいコンクリートとの接着性を確保するために、レイタンスの除去が不可欠である。
コンクリートの品質にもっとも大きなかかわりをもつのは、水セメント比と単位水量である。
必要以上に単位水量の多いコンクリートは、単位セメント量も多くなって不経済であるし、収縮が大きく、また材料分離も起こりやすくなる。
コンクリートの配合は、所要の品質と作業に適するワーカビリティーが得られる範囲内で、単位水量をできるだけ少なくするように定めなければならない。
設計基準強度とは、構造計算において基準とするコンクリートの強度を指し、一般に材齢28日における圧縮強度を基準としている。
コンクリートの配合強度は、現場におけるコンクリートの品質のばらつきを考慮し、現場におけるコンクリートの圧縮強度の試験値が設計基準強度を下回る確率が5%以下になるように定める。
粗骨材の最大寸法は、部材最小寸法の1/5、鉄筋の最小あきの2/3あるいはかぶりの3/4以下とする。
粗骨材の最大寸法は、構造物の種類や鉄筋の配置状況によって適切に選定する必要がある。一般的には、以下の基準が用いられる。
コンクリートのスランプは、運搬、打込み、締固めの作業に適する範囲でできるだけ小さく定める。
適切なスランプ値は、構造物の種類、寸法、鉄筋量、打設方法などによって異なる。一般的には、作業性と強度のバランスを考慮して決定される。
コンクリートは原則としてAEコンクリートとし、AE剤の使用により空気量は多くなり、ワーカビリティーを改善する。空気量は粗骨材の最大寸法、その他に応じて4~7%を標準とする。
AEコンクリートのメリットとしては、以下が挙げられる。
水セメント比とは、コンクリートの配合1m³に使用される水とセメントの配合の質量比(W/C)であり、運搬、打込み、締固めの作業ができる範囲でできるだけ小さくする。
水セメント比の原則は55%以下であり、日本道路公団では水密性や耐久性の観点から配合コンクリートでは55%以下としている。
水セメント比は、コンクリートの強度、耐久性、水密性に大きく影響する要素である。水セメント比が小さいほど、一般的に強度は高くなり、耐久性も向上する。
コンクリートの単位水量は、作業ができる範囲内でできるだけ少なくするようにし、上限値は175 kg/m³を標準とする。
単位水量を抑えることで、以下のメリットがある。
通常のコンクリートでは対応できない特殊な条件下での施工や、特別な性能が求められる場合に、特殊な配合のコンクリートが使用される。
流動化コンクリートとは、あらかじめ練り混ぜられたコンクリートに流動化剤を添加し、攪拌し、流動性を増大させたコンクリートである。単位水量やセメント量を少なくしたい場合に用いる。
流動化コンクリートの主なメリットは、以下の通りである。
膨張コンクリートは、膨張の効果により乾燥収縮等に起因するひび割れを減少させることができ、また、ひび割れ耐力を向上させることができるので、水槽、浄水場、地下構造物、橋梁の床版、トンネル覆工、水密コンクリートなどへの適用が効果的である。
膨張コンクリートは、収縮によるひび割れが問題となる構造物や水密性が要求される構造物に特に有効である。
日平均気温が4℃以下となることが予想されるときは、寒中コンクリートとして施工を行うものとする。
材料を加熱する場合は、水を加熱するのがもっとも容易で、水と骨材を混ぜるときの温度が40℃を超えないように温度を調節し、打込み時に5~20℃のコンクリート温度となるようにする。いかなる場合にも、セメントを直接加熱してはならない。
日平均気温が25℃を超える時期に施工する場合には、暑中コンクリートとして施工しなければならない。
断面の大きい構造物は、セメントの水和熱によるコンクリート内部の温度上昇が大きく、ひび割れを生じやすいので、打込み後の温度上昇がなるべく少なくなるように注意して施工しなければならない。
コンクリートの性質と配合に関する正しい知識は、品質の高いコンクリート構造物を構築するための基礎となる。
本記事では、フレッシュコンクリートの性質、材料分離の問題、配合設計の基本原則、さらには特殊なコンクリートの種類と施工上の注意点について解説した。
特に重要なポイントをまとめると以下のようになる。
これらの知識を活かし、環境条件や用途に適したコンクリートを選定・施工することで、耐久性の高い安全な構造物を実現することができるだろう。
しかし、一言でコンクリートと言っても、その性質や配合は用途に応じて多様に変化する。
本記事では、フレッシュコンクリートの性質から配合の基本原則、さらには特殊な環境や目的に応じた特殊コンクリートの種類まで、幅広く解説していく。
コンクリート工事に関わるエンジニアや技術者はもちろん、建設業界を志す学生にも役立つ情報を提供していく。
1. フレッシュコンクリートの性質
まだ固まっていないコンクリートを「フレッシュコンクリート」と呼ぶ。フレッシュコンクリートは、締固め、仕上げが容易で、これらの作業中において材料分離が少ないものでなければならない。これらの性質を表すために、以下の用語が用いられる。
1-1. ワーカビリティー
ワーカビリティーとは、材料分離を生じることなく、運搬、打込み、締固め、仕上げなどの作業が容易にできる程度を表す性質である。
簡単に言えば、コンクリートの「扱いやすさ」のことだ。
ワーカビリティーの良いコンクリートは、型枠への充填や締固めが容易で、仕上げも綺麗にできる。一方、ワーカビリティーが悪いと、作業効率が落ちるだけでなく、密実なコンクリートを得ることが難しくなる。
1-2. コンシステンシー
コンシステンシーは、フレッシュコンクリートの変形または流動に対する抵抗の程度を表す性質である。コンシステンシーはスランプ試験で求めた値で示される。
スランプ値が大きいほど流動性が高く、小さいほど硬練りであることを意味する。適切なコンシステンシーは、工事の種類や打設条件によって異なる。
1-3. スランプ
スランプは、フレッシュコンクリートの軟らかさの程度を示す指標である。スランプ試験は、一定形状の型枠にコンクリートを詰め、型枠を取り外した際のコンクリートの沈下量を測定するものだ。
コンクリートの運搬、打込み、締固めの作業に適するよう、スランプはできるだけ小さく定める。一般的な鉄筋コンクリート構造物の場合、スランプは8~12cmが標準とされることが多い。
2. 材料分離
コンクリート材料の分離を少なくするためには、適切なワーカビリティーのコンクリートを用いることがもっとも大切であり、分離を減らすために減水剤またはAE剤の活用は極めて有効である。材料分離の代表的なものには以下がある。
2-1. ブリーディング
ブリーディングとは、コンクリートの打込み終了後に、セメントおよび骨材粒子の沈下に伴い水が表面に浮かび上がる現象を言う。
過度のブリーディングは、表面強度の低下、ひび割れの発生、水密性の低下などの原因となる。適切な配合設計と材料選定により、ブリーディングを抑制することが重要である。
2-2. レイタンス
レイタンスとは、ブリーディングに伴い、コンクリートモルタルまたはペーストの表面に、セメント、骨材中の微粒子、セメント水和物等からなる不純物が堆積したものを言う。
レイタンスは弱点にもなるので必ず取り除かなければならない。特に打継ぎ部分では、新しいコンクリートとの接着性を確保するために、レイタンスの除去が不可欠である。
3. コンクリートの配合
3-1. 配合設計の基本
コンクリートの品質にもっとも大きなかかわりをもつのは、水セメント比と単位水量である。
必要以上に単位水量の多いコンクリートは、単位セメント量も多くなって不経済であるし、収縮が大きく、また材料分離も起こりやすくなる。
コンクリートの配合は、所要の品質と作業に適するワーカビリティーが得られる範囲内で、単位水量をできるだけ少なくするように定めなければならない。
3-2. 設計基準強度
設計基準強度とは、構造計算において基準とするコンクリートの強度を指し、一般に材齢28日における圧縮強度を基準としている。
コンクリートの配合強度は、現場におけるコンクリートの品質のばらつきを考慮し、現場におけるコンクリートの圧縮強度の試験値が設計基準強度を下回る確率が5%以下になるように定める。
3-3. 粗骨材の最大寸法
粗骨材の最大寸法は、部材最小寸法の1/5、鉄筋の最小あきの2/3あるいはかぶりの3/4以下とする。
粗骨材の最大寸法は、構造物の種類や鉄筋の配置状況によって適切に選定する必要がある。一般的には、以下の基準が用いられる。
- 一般の場合:20または25mm
- 断面の大きい場合:40mm
- 最小断面寸法が500mm以上かつ、鉄筋の最小あきおよびかぶりの3/4 > 40mmの場合:40mm
- 無筋コンクリート:部材最小寸法の1/4を超えてはならない
3-4. スランプ
コンクリートのスランプは、運搬、打込み、締固めの作業に適する範囲でできるだけ小さく定める。
適切なスランプ値は、構造物の種類、寸法、鉄筋量、打設方法などによって異なる。一般的には、作業性と強度のバランスを考慮して決定される。
3-5. 空気量
コンクリートは原則としてAEコンクリートとし、AE剤の使用により空気量は多くなり、ワーカビリティーを改善する。空気量は粗骨材の最大寸法、その他に応じて4~7%を標準とする。
AEコンクリートのメリットとしては、以下が挙げられる。
- 凍結融解抵抗性の向上
- ワーカビリティーの改善
- ブリーディングの減少
- 材料分離の抑制
3-6. 水セメント比
水セメント比とは、コンクリートの配合1m³に使用される水とセメントの配合の質量比(W/C)であり、運搬、打込み、締固めの作業ができる範囲でできるだけ小さくする。
水セメント比の原則は55%以下であり、日本道路公団では水密性や耐久性の観点から配合コンクリートでは55%以下としている。
水セメント比は、コンクリートの強度、耐久性、水密性に大きく影響する要素である。水セメント比が小さいほど、一般的に強度は高くなり、耐久性も向上する。
3-7. 単位水量
コンクリートの単位水量は、作業ができる範囲内でできるだけ少なくするようにし、上限値は175 kg/m³を標準とする。
単位水量を抑えることで、以下のメリットがある。
- 強度の向上
- 乾燥収縮の低減
- 耐久性の向上
- クリープの減少
4. 特殊な配合のコンクリート
通常のコンクリートでは対応できない特殊な条件下での施工や、特別な性能が求められる場合に、特殊な配合のコンクリートが使用される。
4-1. 流動化コンクリート
流動化コンクリートとは、あらかじめ練り混ぜられたコンクリートに流動化剤を添加し、攪拌し、流動性を増大させたコンクリートである。単位水量やセメント量を少なくしたい場合に用いる。
流動化コンクリートの主なメリットは、以下の通りである。
- 水セメント比を増やさずに流動性を高められる
- ポンプ圧送性の向上
- 締固め作業の省力化
- 密実なコンクリート構造物の構築
4-2. 膨張コンクリート
膨張コンクリートは、膨張の効果により乾燥収縮等に起因するひび割れを減少させることができ、また、ひび割れ耐力を向上させることができるので、水槽、浄水場、地下構造物、橋梁の床版、トンネル覆工、水密コンクリートなどへの適用が効果的である。
膨張コンクリートは、収縮によるひび割れが問題となる構造物や水密性が要求される構造物に特に有効である。
5. 特殊な考慮を要するコンクリート
5-1. 寒中コンクリート
日平均気温が4℃以下となることが予想されるときは、寒中コンクリートとして施工を行うものとする。
【材料】
- セメント:硬化が早く水和熱の大きい早強ポルトランドセメントを用いるのが有利。
- 骨材:骨材に氷雪が混入している場合、コンクリートの単位水量を一定に保つことが困難となるので、骨材はシートなどで覆って貯蔵する。
材料を加熱する場合は、水を加熱するのがもっとも容易で、水と骨材を混ぜるときの温度が40℃を超えないように温度を調節し、打込み時に5~20℃のコンクリート温度となるようにする。いかなる場合にも、セメントを直接加熱してはならない。
【配合】
寒中コンクリートには、できるだけ単位水量の少ないAEコンクリートを用いる。良質のAE剤、AE減水剤あるいは高性能AE減水剤を用いると単位水量を減少できるうえ、適当な空気量を連行することによりコンクリートの耐凍害性も著しく改善される。
寒中コンクリートには、できるだけ単位水量の少ないAEコンクリートを用いる。良質のAE剤、AE減水剤あるいは高性能AE減水剤を用いると単位水量を減少できるうえ、適当な空気量を連行することによりコンクリートの耐凍害性も著しく改善される。
【練混ぜ・運搬および打込み】
打込み時のコンクリート温度は、一般に5~20℃の範囲でこれを定めるとしているが、気象条件が厳しい場合や部材厚が薄い場合には、最低打込み温度は10℃程度確保するのが適当である。
打込み前には、地盤、型枠等のコンクリートから吸熱されそうな部分は十分湿潤状態に保ち、また、型枠、鉄筋等が直射日光を受けて高温となる恐れがある場合には、散水、覆い等の適切な処置を施す必要がある。
打込み時のコンクリート温度は、一般に35℃以下とし、重要な構造物に用いるコンクリートはできるだけ低い温度で打ち込むことが望まれる。
コンクリートは、スランプ低下などの品質変動のなるべく少ない方法によって運搬し、練り混ぜ始めてから打ち終わるまでの時間は1.5時間以内を原則とする。
打込み時のコンクリート温度は、一般に5~20℃の範囲でこれを定めるとしているが、気象条件が厳しい場合や部材厚が薄い場合には、最低打込み温度は10℃程度確保するのが適当である。
打込み前には、地盤、型枠等のコンクリートから吸熱されそうな部分は十分湿潤状態に保ち、また、型枠、鉄筋等が直射日光を受けて高温となる恐れがある場合には、散水、覆い等の適切な処置を施す必要がある。
打込み時のコンクリート温度は、一般に35℃以下とし、重要な構造物に用いるコンクリートはできるだけ低い温度で打ち込むことが望まれる。
コンクリートは、スランプ低下などの品質変動のなるべく少ない方法によって運搬し、練り混ぜ始めてから打ち終わるまでの時間は1.5時間以内を原則とする。
【養生】
コンクリート打込み後、少なくとも24時間は、コンクリートが凍結しないように保護しなければならない。激しい気象作用を受けるコンクリートは、所要圧縮強度が得られるまではコンクリートの温度を5℃以上に保ち、さらに2日間は0℃以上に保つ。なお、寒さが厳しい場合あるいは部材厚さが薄い場合には、これを10℃程度とする。
コンクリートの内外の温度差が大きくならないように、コンクリート表面を断熱性のよい材料(シート等)で覆って保温養生を行う。
コンクリート打込み後、少なくとも24時間は、コンクリートが凍結しないように保護しなければならない。激しい気象作用を受けるコンクリートは、所要圧縮強度が得られるまではコンクリートの温度を5℃以上に保ち、さらに2日間は0℃以上に保つ。なお、寒さが厳しい場合あるいは部材厚さが薄い場合には、これを10℃程度とする。
コンクリートの内外の温度差が大きくならないように、コンクリート表面を断熱性のよい材料(シート等)で覆って保温養生を行う。
5-2. 暑中コンクリート
日平均気温が25℃を超える時期に施工する場合には、暑中コンクリートとして施工しなければならない。
【材料】
練上りコンクリートの温度を低くするためには、なるべく低温度の材料を用いる必要がある。骨材は日光の直射を避けて貯蔵したり、冷却水を用いてできるだけ低温度のものを用いる。
練上りコンクリートの温度を低くするためには、なるべく低温度の材料を用いる必要がある。骨材は日光の直射を避けて貯蔵したり、冷却水を用いてできるだけ低温度のものを用いる。
【配合】
暑中に施工するコンクリートは、減水剤、AE剤、AE減水剤あるいは流動化剤等を用いてできるだけ単位水量を少なくする。
暑中に施工するコンクリートは、減水剤、AE剤、AE減水剤あるいは流動化剤等を用いてできるだけ単位水量を少なくする。
【コンクリートの打込み】
コンクリートを打ち込む前には、地盤、型枠等のコンクリートから吸熱されそうな部分は十分湿潤状態に保ち、また、型枠、鉄筋等が直射日光を受けて高温となる恐れがある場合には、散水、覆い等の適切な処置を施す必要がある。
打込み時のコンクリート温度は、一般に35℃以下とし、重要な構造物に用いるコンクリートはできるだけ低い温度で打ち込むことが望まれる。
コンクリートは、スランプ低下などの品質変動のなるべく少ない方法によって運搬し、練り混ぜ始めてから打ち終わるまでの時間は1.5時間以内を原則とする。
コンクリートを打ち込む前には、地盤、型枠等のコンクリートから吸熱されそうな部分は十分湿潤状態に保ち、また、型枠、鉄筋等が直射日光を受けて高温となる恐れがある場合には、散水、覆い等の適切な処置を施す必要がある。
打込み時のコンクリート温度は、一般に35℃以下とし、重要な構造物に用いるコンクリートはできるだけ低い温度で打ち込むことが望まれる。
コンクリートは、スランプ低下などの品質変動のなるべく少ない方法によって運搬し、練り混ぜ始めてから打ち終わるまでの時間は1.5時間以内を原則とする。
【養生】
コンクリートを打ち終わった直ちに養生を開始し、コンクリートの表面を乾燥から保護し、少なくとも24時間は湿潤状態を保たなければならない。木製型枠等のように表面が乾燥しやすい場合には、型枠も湿潤状態に保つ必要がある。
打込み直後の急激な乾燥によってひび割れが生じることがあるので、直射日光、風等による過度の乾燥を防ぐための散水または覆い等による適切な処置を行う。打込み終了後の初期にひび割れが認められた場合は、再振動やタンピングを行ってこれを除去する。
コンクリートを打ち終わった直ちに養生を開始し、コンクリートの表面を乾燥から保護し、少なくとも24時間は湿潤状態を保たなければならない。木製型枠等のように表面が乾燥しやすい場合には、型枠も湿潤状態に保つ必要がある。
打込み直後の急激な乾燥によってひび割れが生じることがあるので、直射日光、風等による過度の乾燥を防ぐための散水または覆い等による適切な処置を行う。打込み終了後の初期にひび割れが認められた場合は、再振動やタンピングを行ってこれを除去する。
5-3. マスコンクリート
断面の大きい構造物は、セメントの水和熱によるコンクリート内部の温度上昇が大きく、ひび割れを生じやすいので、打込み後の温度上昇がなるべく少なくなるように注意して施工しなければならない。
【材料】
セメントは中庸熱ポルトランドセメントなどの低発熱型セメントを使用する。AE剤、減水剤、AE減水剤または高性能AE減水剤を適切に用いれば、コンクリートのワーカビリティーが改善されるので、単位水量を減らすことができ、それに伴って単位セメント量も減らすことができ、コンクリートの温度上昇を小さくすることができる。
セメントは中庸熱ポルトランドセメントなどの低発熱型セメントを使用する。AE剤、減水剤、AE減水剤または高性能AE減水剤を適切に用いれば、コンクリートのワーカビリティーが改善されるので、単位水量を減らすことができ、それに伴って単位セメント量も減らすことができ、コンクリートの温度上昇を小さくすることができる。
【配合】
単位セメント量は所要のワーカビリティーが得られる範囲でできるだけ少なくする。
単位セメント量は所要のワーカビリティーが得られる範囲でできるだけ少なくする。
【コンクリートの打込み】
コンクリートの打込みは、打込み区画の大きさやリフト高さに注意必要で、構造物の種類によっては、ひび割れ誘発目地により、ひび割れを全く制御する。
コンクリートの打込みは、打込み区画の大きさやリフト高さに注意必要で、構造物の種類によっては、ひび割れ誘発目地により、ひび割れを全く制御する。
【養生】
コンクリートの内外の温度差が大きくならないように、コンクリート表面を断熱性のよい材料(シート等)で覆って保温養生を行う。
コンクリートの内外の温度差が大きくならないように、コンクリート表面を断熱性のよい材料(シート等)で覆って保温養生を行う。
まとめ
コンクリートの性質と配合に関する正しい知識は、品質の高いコンクリート構造物を構築するための基礎となる。
本記事では、フレッシュコンクリートの性質、材料分離の問題、配合設計の基本原則、さらには特殊なコンクリートの種類と施工上の注意点について解説した。
特に重要なポイントをまとめると以下のようになる。
- フレッシュコンクリートの性質(ワーカビリティー、コンシステンシー、スランプ)は、施工性と最終的な品質に大きく影響する。
- 水セメント比と単位水量はコンクリートの品質を左右する最も重要な要素であり、必要以上に増やさないことが重要である。
- 環境条件や構造物の特性に応じて、流動化コンクリート、膨張コンクリート、寒中コンクリート、暑中コンクリート、マスコンクリートなどの特殊なコンクリートを適切に選定する必要がある。
- 特殊なコンクリートを用いる場合は、それぞれの特性を理解し、材料選定、配合設計、施工方法、養生方法など全ての段階で適切な対応が求められる。
これらの知識を活かし、環境条件や用途に適したコンクリートを選定・施工することで、耐久性の高い安全な構造物を実現することができるだろう。
WRITTEN by

建設土木のICT活用など、
デジコンからの最新情報をメールでお届けします