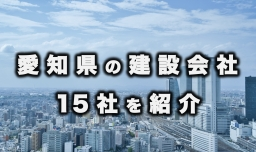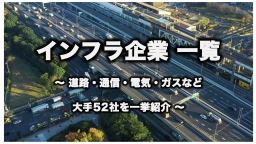建設業をはじめとする様々な業界において、適切な労務管理は企業経営の根幹を成す重要な要素である。
なかでも「労働契約」は、使用者と労働者の関係を規定する基本的な枠組みであり、労働基準法をはじめとする各種法令に則って正しく締結・運用することが求められる。
本記事では、労働契約の基本的な知識や、実務上のポイントについて解説する。
労働契約とは、労働者と使用者の間で交わされる契約であり、労働条件を定めるものである。
労働基準法で定める基準に達しない労働条件は無効となり、その部分については法律で定める基準によることになる。
労働契約に関する基本的な用語について、労働基準法における定義を確認しておこう。
使用者は、労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間およびその後30日間、ならびに産前産後の女性が規定によって休業する期間およびその後30日間は、解雇してはならない。
ただし、使用者が、打切補償を支払う場合または天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りではない。
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。
30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りではない。
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

また使用者は、1週間の各日については、労働者に休憩時間を除き1日8時間を超えて、労働させてはならない。
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
休憩時間は、労働者を代表する者等との協定がある場合を除き、一斉に与えなければならない。また、休憩時間を自由に利用させなければならない。
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
ただし、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において労働時間を延長し、または休日に労働させることができる。
使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
賃金は、通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならない。
賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるものについては、この限りではない。
使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

会社が法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて従業員に残業させたり、休日出勤させたりするには、「36協定」と呼ばれる労使間の協定が必要です。
この協定を結ぶには…
この手続きを正しく行えば、協定の範囲内で残業や休日労働を命じることができる。
ただし、健康に有害な業務(坑内労働など)については、残業時間を1日2時間以内に制限するなどの特別なルールがある。
36協定は、残業させるための「許可証」のようなものであり、これがない状態での残業命令は労働基準法違反となる。
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
また、使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
満18歳に満たない者を深夜(午後10時から午前5時までの間)において使用してはならない。
ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りではない。
使用者は、満18歳に満たない者に以下の危険な作業をさせてはならない。
このように年少者の安全を確保するための就業制限が労働基準法で定められています。
使用者は、満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならない。
以下の女性は坑内作業に従事させてはならない。
産後1年以内で、坑内業務に従事したくないと申し出た女性。また、満18歳以上の女性であっても、次の坑内業務には就かせてはならない。
妊産婦(妊娠中および産後1年以内の女性)には、以下の業務に就かせてはならない。
これらの制限は、女性労働者、特に妊産婦の健康と安全を守るために法律で定められている。
年少者および女性の就労制限については、労働基準法に基づき、詳細な制限業務が定められている。これには以下のような業務が含まれる。
各業務については、年少者(満18歳未満)、妊婦、産婦(産後1年以内)によって、就労可否や条件が異なる。
事業主は、これらの制限を十分に理解し、適切な人員配置を行う必要がある。
実務上、労働契約に関して特に重要ポイントを以下におさらいとしてまとめる。
労働契約は、労働者と使用者の間の権利義務関係を明確にするための重要な枠組みである。
労働基準法をはじめとする労働関係法令では、労働時間や賃金、解雇などについて詳細な規定が設けられており、使用者はこれらの法令を遵守した労働条件を設定し、適切に労務管理を行うことが求められる。

特に建設業においては、現場の安全管理と並んで適切な労務管理が重要であり、法令に則った労働契約の締結・運用が事業の継続的な発展に不可欠である。
また、年少者や女性、妊産婦に対する就労制限についても十分に理解し、適切に対応することが必要である。本記事で解説した基本事項を理解し、適切な労務管理を実践していただきたい。
なかでも「労働契約」は、使用者と労働者の関係を規定する基本的な枠組みであり、労働基準法をはじめとする各種法令に則って正しく締結・運用することが求められる。
本記事では、労働契約の基本的な知識や、実務上のポイントについて解説する。
労働契約の概念と基本用語
1. 労働契約の定義
労働契約とは、労働者と使用者の間で交わされる契約であり、労働条件を定めるものである。
労働基準法で定める基準に達しない労働条件は無効となり、その部分については法律で定める基準によることになる。
2. 基本用語の定義
労働契約に関する基本的な用語について、労働基準法における定義を確認しておこう。
- 労働者: 職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
- 使用者: 事業主または事業の経営担当者その他の事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
- 賃金: 賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
- 平均賃金: これを算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、臨時に支払われた賃金、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は除かれる。
労働契約に関する主要事項
1. 解雇の制限
使用者は、労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間およびその後30日間、ならびに産前産後の女性が規定によって休業する期間およびその後30日間は、解雇してはならない。
ただし、使用者が、打切補償を支払う場合または天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りではない。
2. 解雇の予告
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。
30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りではない。
労働時間、休憩、休日および年次有給休暇
1. 労働時間
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

また使用者は、1週間の各日については、労働者に休憩時間を除き1日8時間を超えて、労働させてはならない。
2. 休憩
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
休憩時間は、労働者を代表する者等との協定がある場合を除き、一斉に与えなければならない。また、休憩時間を自由に利用させなければならない。
3. 休日
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
ただし、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
4. 時間外および休日の労働
災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において労働時間を延長し、または休日に労働させることができる。
5. 年次有給休暇
使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
賃金の支払い
1. 賃金の支払い原則
賃金は、通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならない。
賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるものについては、この限りではない。
2. 非常時払い
使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
3. 休業手当
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

36協定による時間外・休日労働
時間外労働を可能にする36協定
会社が法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて従業員に残業させたり、休日出勤させたりするには、「36協定」と呼ばれる労使間の協定が必要です。
この協定を結ぶには…
《労働者の代表と協定書を作成する》
- 労働組合がある場合は、その労働組合と
- 労働組合がない場合は、従業員の過半数を代表する者と
この手続きを正しく行えば、協定の範囲内で残業や休日労働を命じることができる。
ただし、健康に有害な業務(坑内労働など)については、残業時間を1日2時間以内に制限するなどの特別なルールがある。
36協定は、残業させるための「許可証」のようなものであり、これがない状態での残業命令は労働基準法違反となる。
就労制限に関する規定
1. 年少者の就労制限
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
また、使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
満18歳に満たない者を深夜(午後10時から午前5時までの間)において使用してはならない。
ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りではない。
2. 危険有害業務の就業制限
使用者は、満18歳に満たない者に以下の危険な作業をさせてはならない。
- 運転中の機械や動力伝導装置の危険部分の掃除・注油・検査・修繕
- 運転中の機械や動力伝導装置へのベルトやロープの取付け・取外し
- 動力によるクレーンの運転
- その他、厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務
このように年少者の安全を確保するための就業制限が労働基準法で定められています。
3. 坑内労働の禁止
使用者は、満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならない。
妊産婦に対する就労制限
1. 坑内業務の就労制限
以下の女性は坑内作業に従事させてはならない。
妊娠中の女性
産後1年以内で、坑内業務に従事したくないと申し出た女性。また、満18歳以上の女性であっても、次の坑内業務には就かせてはならない。
- 人力による掘削作業
- その他、女性に有害と厚生労働省令で定められた業務
2. 危険・有害業務の制限
妊産婦(妊娠中および産後1年以内の女性)には、以下の業務に就かせてはならない。
- 重量物を取り扱う業務
- 有害ガスが発生する場所での業務
- その他、妊娠、出産、育児に有害な業務
これらの制限は、女性労働者、特に妊産婦の健康と安全を守るために法律で定められている。
年少者・女性の就労制限業務
年少者および女性の就労制限については、労働基準法に基づき、詳細な制限業務が定められている。これには以下のような業務が含まれる。
- 重量物を取扱う作業:年齢や性別に応じた重量制限がある
- 坑内の作業:年少者は禁止、女性は制限あり
- クレーン、デリック、揚貨装置の運転:女性は5トン以下のみ可能
- 危険な場所での作業:高所作業、土砂崩壊のおそれのある場所など
- 有害物質を扱う作業:粉じん、有害ガスなど
- 高温・多湿環境下の作業
各業務については、年少者(満18歳未満)、妊婦、産婦(産後1年以内)によって、就労可否や条件が異なる。
事業主は、これらの制限を十分に理解し、適切な人員配置を行う必要がある。
労働契約の重要ポイントをおさらい
実務上、労働契約に関して特に重要ポイントを以下におさらいとしてまとめる。
- 賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うものすべてをいう。
- 非常時払いは、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
- 労働時間については、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
- また使用者は、労働者に、1週間の各日については、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
労働契約は、労働者と使用者の間の権利義務関係を明確にするための重要な枠組みである。
労働基準法をはじめとする労働関係法令では、労働時間や賃金、解雇などについて詳細な規定が設けられており、使用者はこれらの法令を遵守した労働条件を設定し、適切に労務管理を行うことが求められる。

特に建設業においては、現場の安全管理と並んで適切な労務管理が重要であり、法令に則った労働契約の締結・運用が事業の継続的な発展に不可欠である。
また、年少者や女性、妊産婦に対する就労制限についても十分に理解し、適切に対応することが必要である。本記事で解説した基本事項を理解し、適切な労務管理を実践していただきたい。
参考元:労働基準法(昭和22年法律第49号)/厚生労働省「労働契約法の解説」/建設業労働災害防止協会「建設業における労務管理の手引き」/画像元:canva
WRITTEN by

建設土木のICT活用など、
デジコンからの最新情報をメールでお届けします