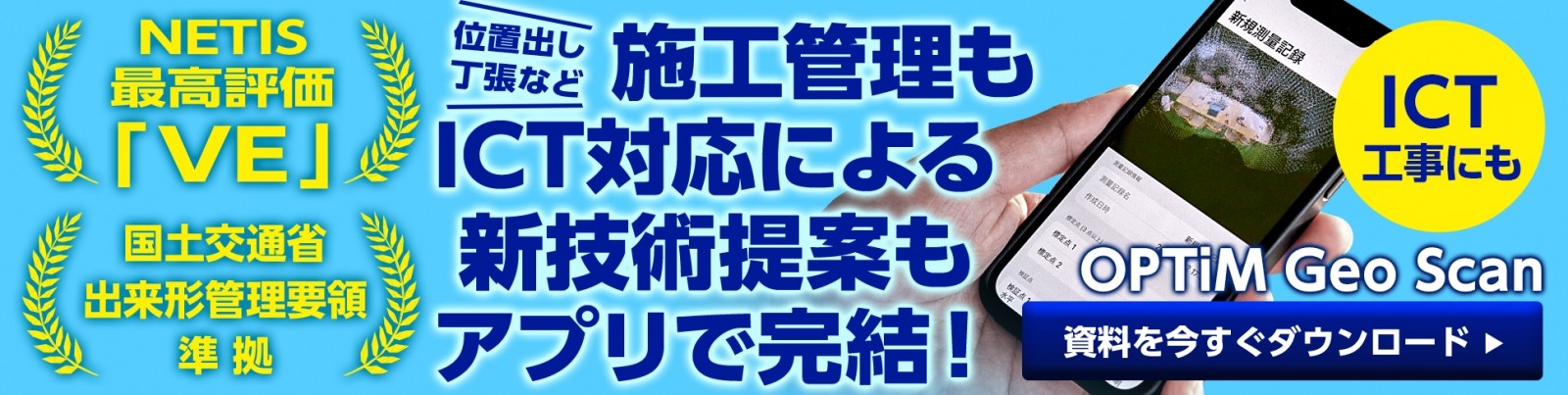ICT基礎知識
ICT測量とは?そのメリットや最新動向も紹介!【2025年】〔測量のことイチから解説〕


はじめに:ICT測量が建設DXを加速させる
あらゆる建設業務は「調査・測量、設計、施工、検査」という一連のプロセスをたどる。
建設DXが推進される現在、この連続したプロセスにICT(情報通信技術)を導入することで、生産性向上と働き方改革の両立が進んでいる。
本記事では、建設事業の入り口にあたる「測量」の現場で、最新のICT技術がどのように活用されているのかについて、2025年の最新動向を踏まえて紹介していく。
ICT測量とは:従来測量との違い
ICT技術が導入される以前、一般的に測量現場では「TS(トータルステーション)」と呼ばれる計測機器を使った測量が行われていた。
「点」として計測されるデータを地道に積み重ね、集計するこの測量方法は、膨大な作業時間と専門技術を要するものだった。
これまで「点」で行われてきた測量を、「面」で行うことで、大幅な効率化を実現したのがICT測量である。
国土交通省の調査によれば、従来型測量と比較して作業時間を最大で70%削減できることが実証されている。
国土交通省によるICT測量の推進状況
国土交通省は、2016年に「i-Construction」を掲げ、建設現場の生産性向上に向けた取り組みを本格化させた。
2025年現在、ICT活用工事は着実に普及が進んでおり、ICT測量はその重要な基盤技術として位置づけられている。
令和6年度(2024年度)の国土交通省直轄工事においては、ICT活用工事の対象工種がさらに拡大され、測量・起工測量におけるICT技術の活用も積極的に推進されている。
また、中小建設業者向けの支援策も拡充されたことで、全国的な普及が加速している。
代表的なICT測量技術
1. UAV(ドローン)写真測量
上空から広範囲を撮影する、ドローン写真測量は、ICT測量の中でも最も普及している手法の一つだ。
"新しい建設機器"とも比喩されるUAV/ドローン(以下、ドローン)は、測量の現場に革命をもたらした。
ドローンにデジタルカメラを搭載し、測量現場を上空から撮影していく。より正確な地形データを収集するため、写真が60~80%重複するように撮影するのが一般的だ。

次に撮影した大量の空中写真を、SfM/MVS(Structure from Motion/Multi-View Stereo)技術を用いた専用のソフトウェアに取り込む。
このソフトウェアが写真の位置関係を解析し、地形の三次元点群データやオルソ画像(空中写真のひずみを補正し、位置情報を付与した画像)を自動的に生成する。
【写真測量の主なメリット】
- 作業時間の大幅削減:例えば、従来なら1週間かかっていた測量作業を1日で完了できる
- 低コストでの導入が可能:ドローン、デジタルカメラ、解析ソフトウェアがあれば始められる
- 安全性の向上:危険な場所に立ち入ることなく測量が可能
- 広範囲の一括測量:広大な面積を効率的に測量できる
【最新動向】
2025年現在、ドローン測量技術はさらに進化している。AI処理による自動解析の精度向上、リアルタイムデータ処理技術の実用化、クラウドサービスとの連携による即時共有システムなどが実装され、より高度な測量が可能になっている。
また、2024年に航空法の改正で新たにレベル4(有人地帯での目視外飛行)が実用化されたことで、都市部でのドローン測量もより柔軟に実施できるようになった。
2. 地上型3Dレーザースキャナー測量
上空から地形データを測量する写真測量に対し、地上から三次元点群データを収集する「地上型3Dレーザースキャナー測量」も広く活用されている。

この測量方法は、1秒間に数千〜数百万発ものレーザー光を照射する3Dレーザースキャナーを測定対象に照射し、反射光の時間差(飛行時間)を元に測定対象の形状を計測する。
従来使用されてきた計測機器「TS(トータルステーション)」も、レーザー照射を用いた計測方法だが、一度の照射で得られるデータが「単点」に留まっていた。
しかし、3Dレーザースキャナーを用いた測量の場合、広範囲の点群データを「面的」に同時計測することができるため、短時間でより詳細な測量が可能になった。最新の地上型3Dレーザースキャナーは、1秒間に200万点以上の点群データを取得できるものもある。
【地上型3Dレーザースキャナー測量のメリット】
- 超高精度な測量:ミリメートル単位の高精度な計測が可能
- 構造物の詳細な再現:建物や構造物の複雑な形状も正確に計測
- 屋内測量にも対応:建物内部や地下空間などの測量も可能
- 昼夜を問わない測量:光量に左右されずに測量作業が行える
【最新動向】
近年、地上型3Dレーザースキャナーはより小型・軽量化が進み、バックパック型やハンドヘルド型の製品も増えている。これにより、一人でも容易に測量作業が行えるようになった。また、計測したデータをリアルタイムで確認できるモバイル連携機能や、AIによる自動分類技術も進化している。
3. UAVレーザースキャナー測量
ドローンによる測量と3Dレーザースキャナー測量、二つの特性を両立する測量法が「UAVレーザースキャナー測量」だ。

使用するのは小型の3Dレーザースキャナー、高精度GNSS(GPSなどの衛星を用いた測位システム)そして加速度を計測するIMU(慣性計測装置)などの機器を搭載したドローン。上空から地上にレーザー光を照射し、広範囲の地形データを瞬時に計測していく。
レーザーを用いることで、写真測量では困難だった樹木が生い茂った森林地帯でも、レーザーが樹木の隙間をすり抜けて地表面の三次元座標を取得することができる。
これにより、従来測量では把握が難しかった森林内の地形も正確に測量できるようになった。
【UAVレーザースキャナー測量のメリット】
- 植生下の地形計測が可能:樹木や草木が生い茂る場所でも地表面データを取得できる
- 高速・広範囲の測量:短時間で広大な面積を計測可能
- 高い精度と効率:写真測量より高精度で、地上レーザーより効率的
- アクセス困難地域の測量:急斜面や水辺など危険な箇所も安全に測量できる
【最新動向】
2025年現在、UAVレーザースキャナーの性能は飛躍的に向上している。
機器の小型軽量化が進み、飛行時間の延長、スキャン精度の向上、点群密度の増加などが実現している。特に最新のUAVレーザーシステムでは、1cm以下の精度で地形測量が可能になっている。
また、マルチスペクトルセンサーとの同時搭載により、地形だけでなく植生分析や環境調査も同時に行えるシステムも実用化されている。
4. MMS(モービルマッピングシステム)
近年普及が進んでいるのが「MMS(Mobile Mapping System)」だ。自動車や列車などの移動体に3Dレーザースキャナーやカメラを搭載し、走行しながら道路や線路周辺の3D点群データを取得するシステムである。
MMSは主に道路や鉄道のインフラ調査に活用されており、効率的な点検や維持管理に大きく貢献している。従来の人力による点検と比較して、安全性も大幅に向上している。
【MMSのメリット】
- 移動しながらの連続測量:走行しながら連続的に3Dデータを取得
- 道路・鉄道の効率的な測量:広範囲の線形インフラを短時間で測量
- 交通規制の最小化:通常の走行で測量できるため交通への影響が少ない
- インフラ点検への活用:路面や構造物の変状検出にも利用可能
【最新動向】
最新のMMSシステムでは、AIによる自動認識技術との連携が進んでいる。例えば、取得した点群データから道路標識や信号機、マンホールなどの道路施設を自動抽出し、台帳整備を効率化するシステムが実用化されている。
また、5G通信との連携により、取得データをリアルタイムでクラウドに送信し、即時処理・共有できるシステムも開発されている。
5. スマートフォン測量アプリ
ICT測量の導入障壁を大きく下げているのが「スマートフォン測量アプリ」だ。
特にiPhoneに搭載されたLiDARスキャナーを活用したアプリは、専門的な測量機器がなくても手軽に3D計測が行える革新的なツールとして注目されている。
OPTiM Geo Scanの概要と機能
株式会社オプティムが開発・提供する「OPTiM Geo Scan」は、iPhone/iPadのLiDARスキャナーを活用した代表的なワンマン測量アプリだ。

2021年にリリースされて以降、継続的な機能強化が行われ、建設・土木現場での活用事例が増えている。
【OPTiM Geo Scanの主な特徴】
国土交通省のi-Construction(ICT活用工事)で求められる3次元データの作成にも対応しており、出来形管理や数量算出にも活用できる。
- iPhoneのLiDARによる3D測量:iPhone 12 Pro以降の機種に搭載されたLiDARスキャナーを利用
- 平面直角座標系の対応:国土地理院が定める平面直角座標系による測量が可能
- GNSSレシーバーとの連携:外部GNSSレシーバーと連携することで、センチメートル級の高精度測位を実現
- 3D点群データの生成:スキャンしながら歩くだけで3D点群データを生成
- クラウドでのデータ管理:取得したデータをクラウド上で管理・共有可能
国土交通省のi-Construction(ICT活用工事)で求められる3次元データの作成にも対応しており、出来形管理や数量算出にも活用できる。
【導入効果】
- 測量時間の大幅削減:従来のTS測量と比較して作業時間を最大60%削減可能
- 導入コストの低減:高価な測量機器に比べ、導入コストを最大80%削減
- 習得の容易さ:直感的な操作性により、専門知識がなくても操作可能
- ワンマン測量の実現:1人での測量作業が可能になり、人手不足対策にも貢献
【スマホ測量アプリの最新動向】
- AI処理の高度化:撮影した写真や点群データをAIが自動処理し、精度向上を実現
- クラウド連携の強化:現場で取得したデータをリアルタイムでクラウドに送信し、オフィスとの情報共有を効率化
- 他システムとの連携:BIM/CIMソフトウェアやCADとの連携により、データ活用の幅を拡大
- 精度向上技術の開発:外部センサーとの連携やアルゴリズム改良による測位精度の向上
【導入事例と効果】
実際の現場では、こうしたスマホ測量アプリがどのように活用されているのだろうか。
例えば、ある中小建設会社では、小規模な道路補修工事の出来形管理にOPTiM Geo Scanを導入した。
従来はTSを用いた測量に半日以上かかっていた作業が、スマホ測量により1時間程度に短縮された。
さらに、測量と同時に3D点群データが生成されるため、出来形の視覚的な確認も容易になり、発注者への説明にも活用されている。
また、災害発生時の緊急測量にも活用されている。2024年の豪雨災害では、被災状況の迅速な把握にスマホ測量アプリが活躍した。
専門的な測量機器の搬入が困難な状況でも、スマートフォン1台で被災範囲や土砂崩れの状況を3Dデータとして記録することができた。
国土交通省の調査によれば、こうしたスマホ測量アプリの活用により、特に中小規模の工事における生産性が向上し、ICT活用工事の裾野拡大に貢献していることが報告されている。
ICT測量データの活用方法
ICT測量で取得した3次元データは、その後の設計・施工・検査・維持管理のプロセスで様々な形で活用されている。
1. 設計段階での活用
- 正確な現況把握:3D地形データをもとに、より正確な設計が可能になる
- 数量算出の自動化:土量計算などを自動で行うことができる
- 設計検討の効率化:3Dモデル上でバーチャルに設計検討ができる
- 関係者との合意形成:視覚的なデータにより、発注者や地域住民との合意形成が容易になる
2. 施工段階での活用
- ICT建機との連携:3D設計データをICT建機に取り込み、自動制御や半自動制御による施工が可能
- 施工シミュレーション:工事の進捗に合わせた施工シミュレーションが行える
- 出来形管理の効率化:3D点群データを活用した出来形管理により、検査の効率化が図れる
- 安全管理の向上:危険箇所を事前に把握し、安全対策を講じることができる
3. 維持管理段階での活用
- 正確な竣工データ:完成時の正確な3Dデータが維持管理に活用できる
- 経年変化の把握:定期的な測量により、構造物の変状や地形の変化を把握できる
- 災害対応への活用:災害前後のデータ比較により、被害状況を正確に把握できる
- アセットマネジメント:点群データを基にした施設管理システムの構築が可能
ICT測量の導入メリットと課題
導入メリット
- 生産性の大幅向上:国土交通省の調査によれば、従来測量と比較して作業時間を最大70%削減可能
- 安全性の向上:危険な場所に立ち入ることなく測量が行える
- 人手不足対策:少人数での測量作業が可能になり、技術者不足への対応策となる
- データの高精度化:面的な取得により、より詳細かつ正確なデータが得られる
- 若手人材の確保:先進技術を活用することで、若手人材を惹きつけることができる
導入時の課題と解決策
- 初期投資コスト課題:機器購入やソフトウェア導入には一定のコストがかかる
- 解決策:国や自治体の補助金活用、リース・レンタル活用、段階的導入
- 技術習得の障壁課題:新技術導入には学習コストと時間がかかる
- 解決策:国土交通省や業界団体による無料講習会の活用、ベンダーの研修プログラム利用
- データ処理環境の整備課題:大量の点群データを処理するには高性能PCが必要
- 解決策:クラウドサービスの活用、処理を外部委託するハイブリッド運用
- 精度管理の課題課題:誤差要因の理解と適切な精度管理が必要
- 解決策:国土地理院のマニュアルに基づく運用、標定点の適切な設置
中小建設業者向けICT測量導入のステップ
ICT測量の導入を検討している中小建設業者向けに、段階的な導入ステップを紹介する。
STEP1:情報収集と計画立案
- 国土交通省や地方整備局のセミナーや講習会への参加
- 先行導入企業の見学や情報交換
- 自社に適したICT測量技術の選定
STEP2:試験導入
- 小規模な現場での試験的導入
- レンタル機器の活用による初期投資の抑制
- 社内研修や人材育成の実施
STEP3:本格導入と展開
- 成功事例を基にした本格導入
- ICT活用工事への積極的な取り組み
- データ活用の拡大と業務プロセスの見直し
STEP4:高度化と応用
- 他のICT技術との連携(BIM/CIM、ICT施工など)
- データ資産の蓄積と活用
- 新たなビジネスモデルの創出
最新事例:ICT測量の活用実績
事例1:災害復旧工事での活用
2024年に発生した大規模災害の復旧工事では、UAVレーザー測量が大きな威力を発揮した。立入禁止区域も含めた広範囲の被災状況を短期間で把握し、復旧計画の迅速な立案に貢献した。また、定期的な測量により、復旧工事の進捗管理も効率的に行われた。
事例2:中小企業での導入成功例
岐阜県の中堅建設会社A社は、ドローン写真測量を段階的に導入し、測量作業の効率化に成功。測量に要する時間を従来の3分の1に削減するとともに、若手社員の積極的な参加により技術継承の問題も解消しつつある。
事例3:都市インフラ管理での活用
東京都内の道路管理業務では、MMSを活用した効率的な路面調査が実施されている。取得したデータはAIで解析され、舗装の劣化や道路付属物の損傷を自動検出。維持管理計画の策定に大きく貢献している。
今後の展望と発展方向
ICT測量技術は、今後もさらなる進化が期待される。特に以下の点において発展が見込まれる。
- AI・自動化技術との融合点群データの自動分類・認識技術の高度化
- 測量計画の自動最適化システムの実用化
- リアルタイム処理・共有の実現5G/6G通信を活用したリアルタイムデータ転送
- エッジコンピューティングによる現場でのデータ処理
- マルチセンサー統合による高度化レーザー、光学、熱赤外線など複数センサーの統合
- 地上・空中データの自動統合技術の確立
- デジタルツイン構築への貢献都市・インフラのデジタルツイン構築における基盤データとしての活用
- 4D(時間軸を含む)測量データの活用
まとめ:ICT測量がもたらす建設業の未来
ICT測量技術は、建設業界のデジタルトランスフォーメーション(DX)を牽引する重要な技術として、急速に普及が進んでいる。
従来の「点」での測量から「面」での測量へと進化したことで、測量作業の大幅な効率化と安全性向上が実現されている。
ドローン写真測量、地上型3Dレーザースキャナー、UAVレーザー測量、MMSなど、様々な技術が開発・実用化され、現場のニーズに応じた選択が可能になっている。
さらに、これらの技術から得られる3次元データは、後続の設計・施工・検査・維持管理プロセスでも活用され、建設生産システム全体の効率化に寄与している。
国土交通省のi-Constructionの取り組みもあり、ICT測量は中小建設業者にも広がりつつある。
初期投資や技術習得の障壁はあるものの、段階的な導入や支援制度の活用により、多くの企業が導入に成功している。
今後は、AI技術との融合やリアルタイム処理・共有の実現、マルチセンサーの統合などにより、さらなる進化が期待される。
WRITTEN by

高橋 奈那
神奈川県生まれのコピーライター。コピーライター事務所アシスタント、広告制作会社を経て、2020年より独立。企画・構成からコピーライティング・取材執筆など、ライティング業務全般を手がける。学校法人や企業の発行する広報誌やオウンドメディアといった、広告主のメッセージをじっくり伝える媒体を得意とする。
大人気シリーズ!【いまさら聞けない?】測量のことイチから解説 〜 連載記事一覧 〜
- ICT測量とは?そのメリットや最新動向も紹介!【2025年】〔測量のことイチから解説〕